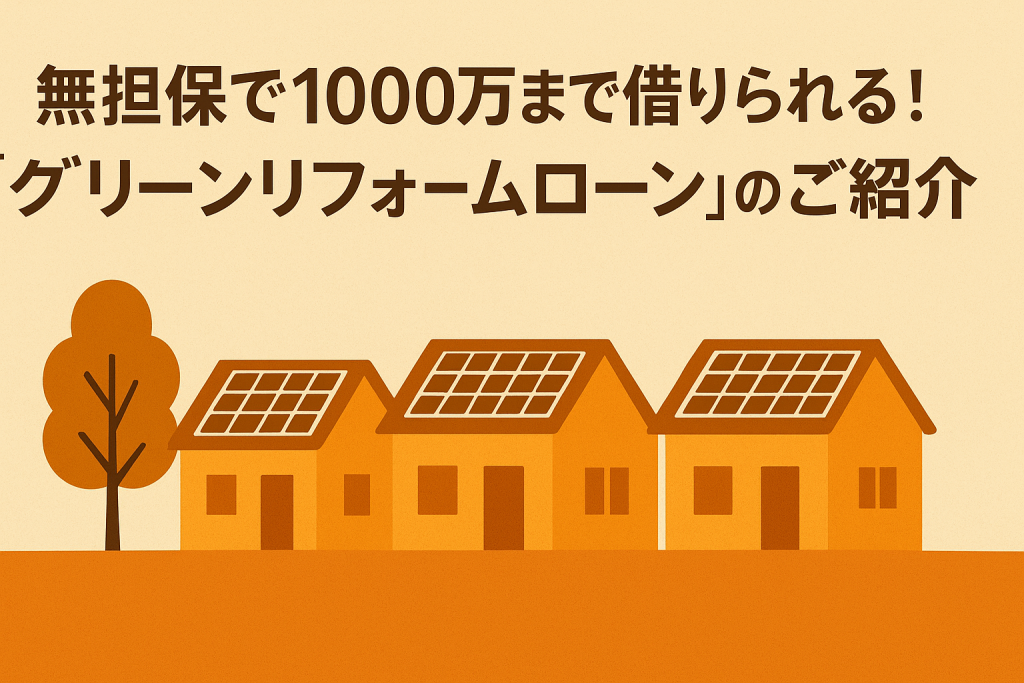
今、「自宅をもっと快適に」「冬寒く夏暑い家を改善したい」「光熱費を抑えたい」といったお声を、特に冬を迎えるこの時期に多く頂きます。
そんな皆さまに、国の制度「グリーンリフォームローン(日本住宅金融支援機構)」をご活用いただくことで、省エネ・断熱改修を含むリフォームを後押しできます。本記事では、制度の概要、メリット・注意点、活用のポイントを分かりやすくご紹介します。
1|グリーンリフォームローンとは?
「グリーンリフォームローン」は、住宅の断熱性・省エネルギー性能を高める工事を対象とするリフォーム資金の融資制度です。
従来のリフォームローンと比べて、無担保・無保証、全期間固定金利など利用しやすい条件が特徴です。
2025年10月以降、融資上限額が500万円から1,000万円に引き上げられるなど、制度が拡充されました。
また、省エネ性能をより高い水準に引き上げるリフォーム(たとえば、ZEH水準を満たす断熱改修など)を行う場合には、グリーンリフォームローンSとして、通常のローンより有利な金利が適用されます。
2|主な条件とポイント
以下、制度利用にあたっての主要な要件・ポイントを整理します。
融資上限額・返済期間
- 融資上限:最大1,000万円(10 万円以上、1 万円単位)
- 返済期間:最長10年以内、全期間固定金利型(借入時に返済期間中の金利が決定)
- 担保・保証人・融資手数料:原則不要(ただし、高齢者向け返済特例制度を利用する場合は要担保)
- 団体信用生命保険:加入可能(条件により異なる)
利用できる人・対象住宅
- 利用者:借入申込時の年齢が満79歳未満(親子リレー返済利用可)
- 返済負担率:年収が400万円未満なら30%以下、400万円以上なら35%以下など(他の借入も含めて総返済額基準あり)
- 対象住宅:
・自分が居住する住宅
・セカンドハウス(週末利用住宅など)
・親族居住住宅(申込者または配偶者の直系親族など) - 対象工事(いずれか必須)
1. 断熱改修工事(窓・壁・屋根・床など)
2. 省エネ設備設置工事(高効率給湯機、太陽光発電、太陽熱利用、高断熱浴槽、コージェネ設備など) - 併用工事:上記省エネ工事と併せて、キッチン・バス・トイレなどの水回り改修や外装工事も、条件内で融資対象とすることが可能。ただし、その他工事の融資上限は省エネ工事費と同額まで。
適合証明・検査手続き
リフォーム工事を実施する前に、適合証明検査機関に工事計画を申し込み、現地調査・工事後検査を受け、適合証明を得る必要があります。
適合証明作成には所定の手数料がかかり、利用者負担となります。
なお、リフォーム業者団体と機構との協定により、一定条件下で検査を省略可能な場合もあります。
高齢者向け返済特例(ノンリコース型)
満60歳以上の方は、毎月の返済を「利息のみ」にできる高齢者向け返済特例が利用可能です。元金返済は、申込者が亡くなった後に相続人が一括返済、もしくは担保住宅売却代金から清算されます。債務超過リスクを相続人に残さない「ノンリコース型」として扱われることが特徴です。
ただし、この特例を使う際には担保が必要で、団体信用生命保険には加入できないケースがあります。
3|利用メリット・魅力
この制度を活用することで得られるメリットを以下に整理します。
① 低リスク・計画しやすい返済条件
無担保・無保証・融資手数料不要という条件のもと、定額返済(全期間固定金利)で返済計画を立てやすい点が魅力です。
② 省エネ改修による光熱費軽減・快適性向上
断熱性能を高めたり高効率設備を導入したりする工事を通じて、冷暖房や給湯のエネルギー消費を抑制できます。これにより長期的には光熱費負担を軽減でき、住空間としての快適性(ヒートショック防止、冷房効率向上など)も改善できます。
③ より幅広いリフォームとの併用が可能
省エネ改修と同時にキッチンやお風呂、窓・外壁の交換といった通常のリフォームを併せて行いたい場合、併用対象部分も一定比率で融資対象にできる点が実用的です。
④相続リスクの軽減(高齢者向け特例利用時)
高齢者向け返済特例を活用すれば、残債が発生しても相続人が返済義務を負わない形式(ノンリコース型)となるため、万が一の際の家族への負担を抑えられます。
4|注意点・留意すべきポイント
制度を無理なく活用するためには、以下の点にも注意しておいてください。
適用可否・工事の要件確認が不可欠
すべてのリフォームが対象になるわけではなく、省エネ基準を満たす断熱改修や設備導入工事を含むことが必須です。特にZEH水準を目指す場合は、開口部・壁・天井・床すべての条件をクリアしなければなりません。
融資上限に注意
併用リフォームを行う場合、その他の工事部分の融資枠は省エネ工事費と同額までという制約があります。たとえば省エネ工事に300万円を使うなら、それ以外のリフォーム工事も最大300万円までしか融資対象にはなりません。
審査・支払能力の確認
他ローンとの借入状況、返済負担率、信用情報等が審査され、希望通り融資を受けられない可能性もあります。
また、適合証明取得後に工事内容が設計どおりでない、工事中止などになった場合、融資が受けられないリスクがあります。
高齢者向け特例のデメリット
利息のみ返済の期間を選べる反面、元金返済が将来に繰り延べられるため、最終的な返済負担を確認する必要があります。また、担保が必要であったり団体信用生命保険が適用されない場合があります。
5|事例イメージ
たとえば、あるお宅で「断熱改修(窓交換+壁断熱補強)+システムキッチン交換+浴室改装」を計画したとします。
省エネ改修に200万円、その他リフォームに150万円の見積が出た場合、この制度では「省エネ改修費の200万円」までが確実に融資対象になります。そしてその他工事部分(150万円)も、省エネ改修費と同額まで融資可能ですので、合計で350万円の融資まで対応可能です(上限1,000万円の範囲内で)。
このように、住まい全体を総合的にアップデートしつつ、省エネ性を高めることができる点がこの制度の魅力です。
6|こんな方におすすめ
- 冬寒く夏暑い住宅を抱えていて、断熱性や省エネ性能を高めたい
- 光熱費負担を抑えたい、快適性を向上させたい
- リフォームと省エネ改修を同時に行いたい
- 将来的な相続リスクを抑えたい高齢の方
- 長期固定で返済計画を明確に立てたい方
7|まとめ
担保なしで1000万まで固定金利で借りられる住宅ローンはなかなかありません。
ご自宅をリフォームする手段としていかがでしょうか?
出典:日本住宅金融支援機構「グリーンリフォームローン」



 オンライン相談
オンライン相談 資料請求
資料請求 お問い合わせ
お問い合わせ